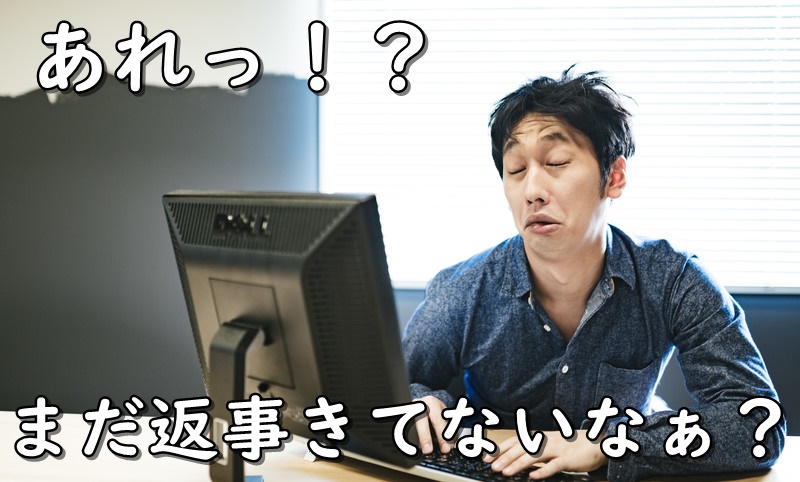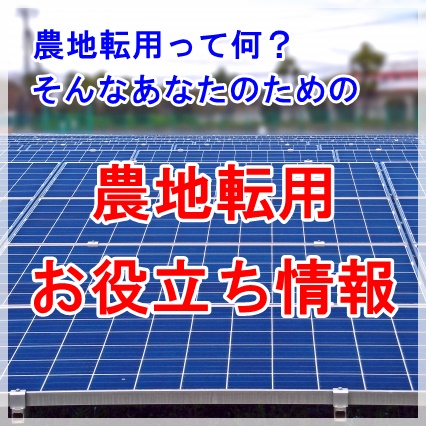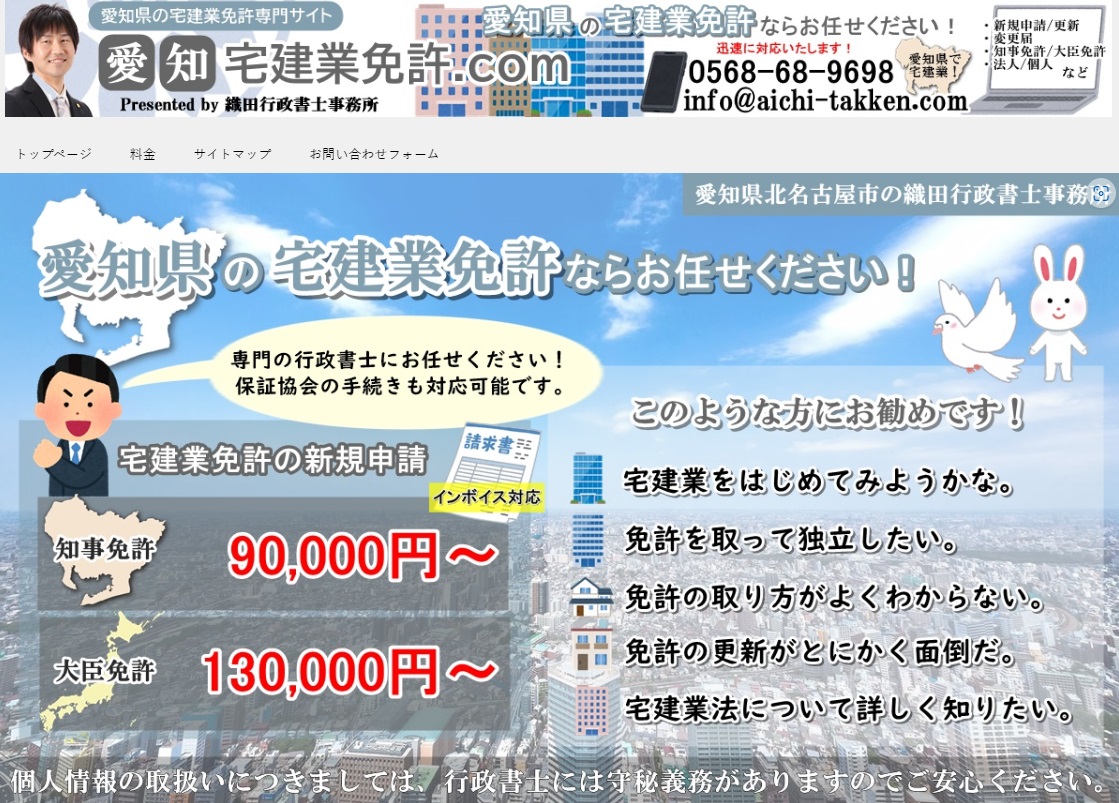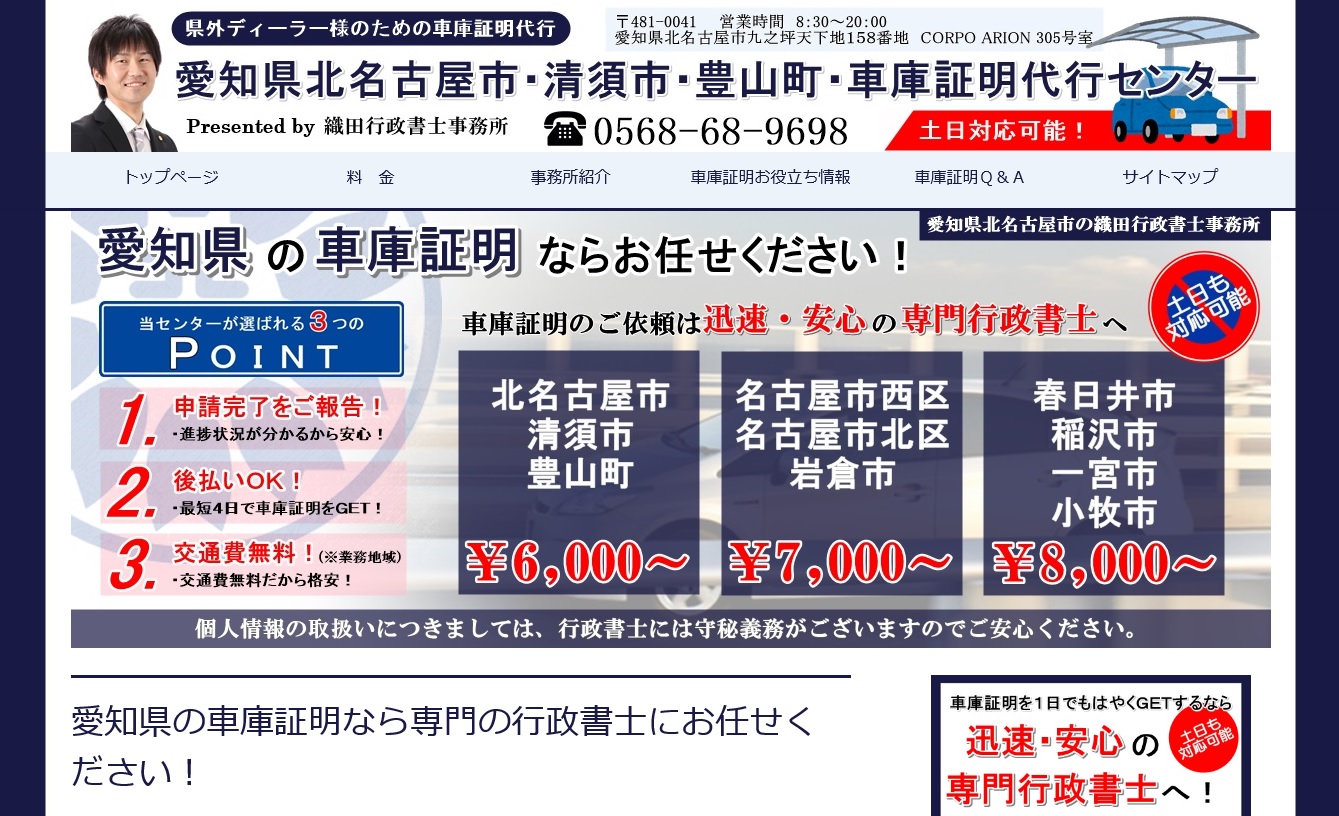数年前になるのですが、当サイトをガッツリ盗用していたサイトを発見し(しかも割と近所)、あまりに悪質だったため情報公開をして撃退したということがありました。
このように弊所はしばしばホームページの内容を盗用されることがあり、そのたびに頭を悩ませています。
そして、再び見つけてしまいました。
今回はまるパクリとは言えませんが、まるパクリにならないようにいろいろ努力されたことが伝わってきます。念のためオリジナルと比較してみて、「あれま~」という感じです。
ところでなぜ盗用と分かるのか?
それは簡単です。
弊所はホームページを作成する前にまず法律書や専門書(これがなかなか高額!)を読んで法律知識をつけ、その内容を噛み砕いてとにかく読者の方が理解しやすいように文章構成を考えたり言葉選びをしています。難しい言葉を使わざるを得ないときは、別枠でその言葉の説明文を入れたりもしています。
記事を作成してもすぐには公開しません。何度か読み返しておかしいところ、分かりにくいところはないかチェックをしてからはじめて公開しています。
ここまで労力をかけてようやく1つの記事にしているわけですから、文書を読めばすぐに自分の言葉(思考回路)であることがすぐに分かってしまうわけです。
そもそも行政書士は、その専門的な法律知識が商売道具となる仕事です。その最も重要な部分を省いて集客し、依頼を獲得しようとする神経を理解することができません。
依頼人に対して失礼だとは思わないのでしょうか?